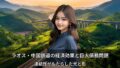タイが2024年に世界第6位のレアアース生産国となった。米国地質調査所のデータによると、生産量は前年比261%増の13,000トンに達している。10月26日に米国と署名した重要鉱物サプライチェーン協力覚書は、この成長を後押しする要因となっている。しかし、この機会の裏には、ミャンマーから流入する環境汚染という現実的な課題が存在する。
急浮上した背景と実態
2024年のタイのレアアース生産量13,000トンは、2023年の3,600トンから約3.6倍に増加した。この数値により、タイは中国、米国、ミャンマー、オーストラリア、ナイジェリアに次ぐ世界第6位の生産国となった。
表1.1:世界の主要レアアース生産国の鉱山生産量(REO換算、トン)、2020年~2024年
| 国名 | 2020年 | 2021年 (推定) | 2022年 | 2023年 | 2024年 (推定) | 2023-2024年 変化率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国 | 140,000 | 168,000 | 210,000 | 255,000 | 270,000 | +5.9% |
| 米国 | 39,000 | 43,000 | 42,500 | 41,600 | 45,000 | +8.2% |
| ミャンマー | 31,000 | 26,000 | 71,000 | 43,000 | 31,000 | -27.9% |
| オーストラリア | 21,000 | 22,000 | 18,000 | 16,000 | 13,000 | -18.8% |
| ナイジェリア | N/A | N/A | N/A | N/A | 13,000 | N/A |
| タイ | 3,600 | 8,000 | 7,100 | 3,600 | 13,000 | +261.1% |
| マダガスカル | 2,800 | 3,200 | 9,600 | 7,200 | 13,000 | +80.6% |
| ロシア | 2,700 | 2,700 | 2,600 | 2,500 | 2,500 | 0.0% |
| インド | 2,900 | 2,900 | 2,900 | 2,900 | 2,900 | 0.0% |
| ベトナム | 700 | 400 | 4,300 | 1,200 | 300 | -75.0% |
出典:米国地質調査所(USGS)のMineral Commodity Summariesおよび各種報道機関のデータを基に作成。2024年の数値は推定値を含む。
ただし、タイ鉱業・基盤産業局のアディタット局長は「商業的に採算が取れるほどの鉱床はまだ見つかっていない」と公式に述べている。タイは主にレアアースを輸入して加工している。現在の生産統計は、国内での新規採掘よりも、輸入した原料または半加工品を処理する加工能力を反映したものである。
ナコーンラーチャシーマー県には、ネオ・マグネクエンチ社の高性能永久磁石製造工場が存在する。このような施設は、タイの強みが上流の採掘ではなく、中流から下流の加工にあることを示している。中国のEVメーカーBYDも、同県にEV生産工場とモーター用磁石製造工場への投資を行っている。
米・タイ覚書の内容と国内の反応
10月26日、マレーシアのクアラルンプールで開催された第47回ASEAN首脳会議において、タイのアヌティン首相と米国のトランプ大統領が「重要鉱物サプライチェーンの多様化と投資促進に関する協力覚書」に署名した。
覚書の協力範囲は、重要鉱物およびレアアースの探査、抽出、加工、精製、リサイクル、回収といった資源のライフサイクル全体を網羅している。具体的な協力分野として、タイの資源基盤の分析、技術的専門知識の共有、政府間会合や共同地質科学調査の実施、許認可プロセスの合理化、公正な貿易慣行の協調が含まれる。
政府関係者は国際法上法的拘束力を持たないことを一貫して強調している。MOU本文第3項にも「この覚書は国際法の下で法的に拘束力を持つことを意図していない」と明記されている。法制審議会は、タイ憲法第178条に定める「条約」には該当せず、国会承認は不要との公式見解を示した。
覚書で最も議論を呼んでいるのが、米国に「投資する最初の機会」を与える条項である。ホワイトハウスが公開した原文によれば、タイ国内で売却される可能性のある重要鉱物資産について、米国がタイの国内法に従って「最初の投資機会を持つことが期待される」と記されている。
野党からは批判が上がっている。人民党のパッタラポン議員や民主党のウェラポン副党首らは、タイ側が米国で相互に投資を行うことはコストや技術力の面で非現実的であり、実質的に不平等な内容だと指摘している。また、このMOUがタイを米中対立の駒にし、北京からの報復を招く可能性があるという懸念も表明されている。
スパジー商務大臣は、この覚書がタイに地政学的な選択を強いるものではないと強調している。中国がタイの最大の貿易相手国であり、米国が最大の輸出市場であるという現実を指摘し、将来的には中国と同様の協力覚書を締結する可能性も排除しないと述べている。
米中のサプライチェーン競争
この覚書は、レアアースを巡る米中の地政学的競争という大きな構図の中に位置づける必要がある。レアアースは、EV、風力タービン、スマートフォン、最新鋭ミサイル誘導システムといった製品に不可欠な17種類の元素群である。
中国は世界のレアアース埋蔵量の推定70~85%、そして精製・加工能力の約90%を掌握している。中国政府は近年、輸出許可や報告義務を課すなど輸出規制を強化し、事実上サプライチェーンを武器化している。
米国は、中国への依存を低減するため、サプライチェーンの多様化戦略を積極的に推進している。米・タイ間の覚書は、中国が輸出規制の強化を発表した直後に署名された。米国は、タイをマレーシアと共に、中国の直接的な管理外にあるASEAN域内の「相互接続された地域供給ネットワーク」を構築するという戦略において、中心的な柱と見なしている。
米国はタイとの覚書締結と並行して、マレーシア、ベトナム、フィリピン、インドネシアといった国々とも同様の協力関係を模索している。マレーシアとは貿易協定を締結し、レアアースの安定供給に関する確約を取り付けた。オーストラリアとは、レアアース開発プロジェクトに数十億ドル規模の共同投資を行う包括的な枠組みを構築している。
タイの資源潜在性
タイの国土には、地質学的にレアアース鉱物が存在する可能性が認められている。最近の関心は、タイ東北地方、特にナコーンラーチャシーマー県とブリーラム県に集中している。地質調査によると、この地域の堆積層には、磁石の原料として重要なネオジム、プラセオジム、ジスプロシウム、イットリウムなどの元素が豊富に含まれている可能性が示されている。
タイ南部のプーケットにおける風化した花崗岩プロファイルでは、世界的に重レアアースの主要な供給源である価値の高いイオン吸着型粘土鉱床がすでに確認されている。東北地方でも、REEを含む原岩が風化し、その後の堆積プロセスを経て同様の鉱床が形成される可能性がある。
歴史的には、モナザイトやゼノタイムといったレアアース含有鉱物が、特にタイ南部および西部の花崗岩帯における錫やタングステンの採掘の副産物として発見されてきた。これらの鉱物は、一次鉱床および漂砂鉱床の両方で見つかっている。
タイのレアアースポテンシャルは、東北地方の堆積型鉱床、南部と西部のモナザイト/ゼノタイムの鉱床、そして風化した花崗岩地域における高価値のイオン吸着型粘土鉱床の可能性という、少なくとも3つの異なるタイプで構成されている。
しかし、これらの鉱床の商業的実行可能性には大きな疑問符が付いている。資源が地質学的に存在することと、それが経済的に採掘可能な「埋蔵量」であることとは別問題である。タイ政府は鉱物資源局が中心となって、2026年の完成を目指し、全国的な資源ポテンシャルマップの作成を進めている。
ミャンマーからの環境汚染
環境面での懸念は特に深刻である。タイ北部のチェンマイ県やチェンライ県では、隣国ミャンマーでの中国系企業による無規制なレアアース採掘が原因とみられる河川の重金属汚染が深刻な問題となっている。
ミャンマー・カチン州では、2021年の軍事クーデター以降、違法かつ無規制なレアアース採掘が爆発的に増加した。中国政府が自国内の環境規制を強化したことに伴い、汚染度の高い採掘工程がミャンマーに事実上移転されたという構造がある。
採掘現場では、硫酸アンモニウムや塩化アンモニウムといった化学薬品が大量に注入される。使用後の有毒な廃液は、適切な処理施設がないため、そのまま河川や土壌に垂れ流されている。1トンのレアアースを生産するために、最大2,000トンの有毒廃棄物が発生する可能性があり、これには危険な化学物質、重金属、そしてトリウムやウランといった放射性元素が含まれる。
カチン州やシャン州の鉱山から流出した汚染水が、国境河川を通じてタイ北部に流入している。タイ側の調査では、河川水や農作物から基準値を超えるヒ素などの重金属が検出されており、タイ国内の農業、漁業、観光業に推定4,000万ドルの経済的損害を与えていると報告されている。
タイは鉱業による環境影響の管理において、過去に課題を抱えてきた。ナコーンシータンマラート県での錫採掘によるヒ素中毒、カンチャナブリー県での鉛採掘による鉛中毒、ターク県での亜鉛採掘によるカドミウム中毒といった事例が記録されている。
タイ東北地方では、カリ鉱山や石切り場に対する地域社会の強い反対運動の歴史がある。環境破壊、土壌の塩類化、生活への影響などがその理由として挙げられている。新たな大規模鉱業が開発されれば、同様の土地利用を巡る対立が引き起こされる可能性は極めて高い。
加工ハブとしての方向性
タイの躍進は、単なる地質学的発見の物語というよりも、意図的な産業政策と地政学的な位置づけの成功物語と見るべきである。タイの経済モデルは、未加工の資源を輸出する採掘型から、加工された材料や磁石を販売する産業付加価値型へと移行している。
オーストラリアに拠点を置くライナス・レアアース社は、タイ西部のカンチャナブリ県において、レアアース加工工場の建設に向けた事業化調査を進めている。ただし、同社はマレーシアのクアンタン市にある精製工場において、操業に伴い発生する低レベル放射性廃棄物の処理を巡って、長年にわたり地元住民や環境団体との間で深刻な対立を抱えてきた実績がある。
興味深い視点として、タイ国内の錫製錬大手企業タイサルコ社は、プーケット県やパンガー県など、かつて錫鉱山で栄えた地域の尾鉱から、レアアースを含む有用鉱物を回収する技術開発を検討している。過去の産業廃棄物を二次資源として再利用するアプローチは、環境負荷を低減できる可能性がある。
今後の展望
タイは現在、重要な岐路に立っている。覚書が提示する選択肢は、経済発展と産業高度化への機会である一方、環境破壊や外交的バランスを失うリスクも内包している。
商業化が実現すれば、レアアース産業はタイのGDP、税収、外貨獲得に貢献する可能性がある。世界銀行は、エネルギー転換に必要な鉱物分野への投資が世界全体で1.7兆ドルに上ると試算している。タイが単なる資源輸出国に留まらず、レアアースを用いた高付加価値製品の製造拠点へと産業構造を高度化させることが重要となる。
一方で、採掘よりも加工を優先する戦略が考えられる。技術移転を活用し、高度な雇用を創出する高付加価値の加工ハブとなる方向性である。規制能力が証明されるまでは、大規模な国内採掘については慎重な検討が必要となる。
ミャンマーからの汚染危機は、規制が不十分なレアアース採掘がもたらす環境への影響をリアルタイムで示している。タイ政府がこの外部からの脅威に効果的に対処できていない現状は、同種の国内産業を規制する能力に課題があることを示唆している。
BKK IT Newsの視点としては、タイが最も厳格な環境・社会基準を遵守する持続可能なレアアースの供給国というブランドを確立する道筋が考えられる。独立した規制・監視機関の設立、情報公開と国民参加の徹底、尾鉱からの再資源化技術への集中投資といった選択肢である。また、マレーシアやベトナムなど同様の課題に直面しているASEAN諸国と緊密に連携し、共通の環境・社会基準を策定することで、大国に対する共同の交渉力を高める方向性もある。
タイ政府の今後の対応が、この覚書を持続可能な発展への第一歩とするか、新たなリスクの入口とするかを決定することになる。
参考記事リンク
- Unearthing Thailand’s rare earth treasure: where are they hidden?
- Thailand Warned Against Monopolistic US Rare Earth Deal in ‘Trade War’ Fallout
- More Thai rivers and downstream communities at risk from Myanmar’s rare earth mines
- US-Thailand Rare Earth Partnership Reshapes Global Supply Chains – Discovery Alert
- RARE EARTHS – USGS.gov