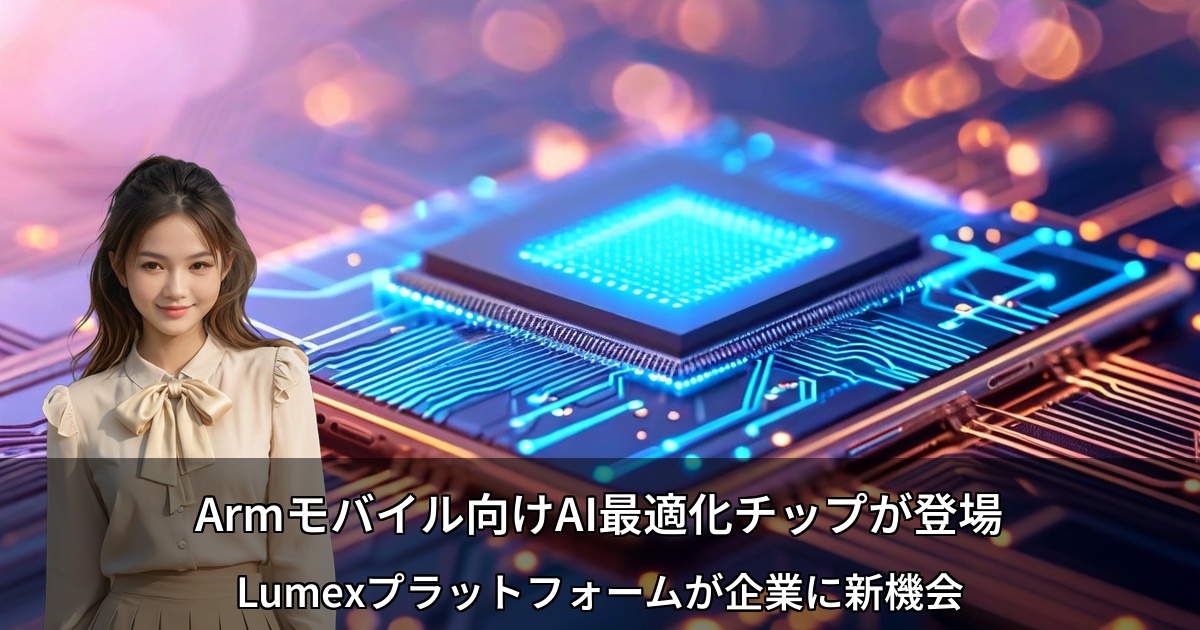半導体設計大手のArmが発表した新たなモバイル向けAI最適化プラットフォーム「Lumex」が、企業のスマートフォン製造とソフトウェア開発に大きな変化をもたらそうとしている。CPU中心のAI処理戦略により開発コスト削減と性能向上を両立し、中小規模メーカーでも高度なAI機能の実装が可能になる。
2025年9月10日、半導体設計大手のArmが新たなモバイル向けAI最適化プラットフォーム「Lumex Compute Subsystem (CSS)」を発表した。この発表は、企業のデジタル競争力向上に重要な転換点をもたらす可能性がある。
モバイルAI処理の進化過程
近年のスマートフォンでは、AI処理の需要が急激に拡大している。従来、AI処理は主にクラウドサーバーで実行されていたが、プライバシー保護やリアルタイム性の要求により、デバイス内での処理(オンデバイスAI)が重要になった。
この流れを受けて、QualcommやAppleは専用のAI処理チップ(NPU)を開発してきた。しかし、NPUは製造コストが高く、各社のアーキテクチャが異なるため、ソフトウェア開発者にとって負担となっていた。こうした課題を背景に、ArmはCPU中心のAIアクセラレーション戦略を採用した。
Lumex CSSプラットフォームの技術仕様
今回発表されたLumexの最大の特徴は、「Compute Subsystem」として提供される点である。従来のように個別のCPUやGPUを別々にライセンスするのではなく、事前に統合・検証済みのサブシステムとして提供する。これにより、チップメーカーの開発期間を最大12ヶ月短縮できるという。
新しい「C1」CPUコアファミリーは、4つの異なる性能レベル(C1-Ultra、C1-Premium、C1-Pro、C1-Nano)を用意している。最高性能のC1-Ultraは、前世代と比較してシングルスレッド性能が最大25%向上している。
最も注目すべきは「Scalable Matrix Extension v2(SME2)」という新命令セットである。これはCPUコアに直接実装されたAIアクセラレーション機能で、AI処理性能を最大5倍向上させる。音声認識や言語処理においては、レイテンシが4.7倍低減されることが実証された。
新設計のMali-G1 GPUも、グラフィックス性能が20%向上し、AI推論性能も20%向上している。3nmプロセス技術に最適化されており、高い性能を維持しながら消費電力を抑制する。
市場競争への影響
Lumexの登場により、2026年以降のスマートフォン市場では新たな競争構図が生まれる。MediaTekやSamsungなどのチップメーカーは、Lumex CSSプラットフォームを採用することで開発効率を大幅に向上させられる。
一方で、独自CPU設計のQualcommや垂直統合のAppleとの競争も激化する。AI処理において「強力なCPU+NPU」というArmのアプローチが、「カスタムCPU+専用NPU」という従来のアプローチと真正面から競合することになる。
Googleなどの主要ソフトウェアベンダーがすでにSME2対応を完了していることから、エコシステム全体での採用が加速する見込みだ。
今後の展望
BKK IT Newsでは、Lumexプラットフォームの普及により、スマートフォン製造業界に新たな機会が生まれると予測している。統合されたCSSにより、開発コストを削減できるため、中小規模のメーカーでも高性能なAI機能を搭載したデバイスを開発しやすくなる。
また、Armは次世代PC向けの「Arm Niva」ブランドも準備しており、モバイル以外の分野への展開も加速する可能性がある。特に、バッテリー持続時間で優位に立つArmアーキテクチャは、ノートPCでも競争力を発揮するだろう。
ただし、最先端の3nmプロセス製造はTSMC(台湾積体電路製造)に依存しており、地政学的リスクという課題も存在する。
企業への戦略的示唆
企業にとって、Lumex CSSプラットフォームの登場は複数の戦略的選択肢を提供する。まず、デバイスメーカーは開発リソースを削減し、UI/UXやサービス開発に集中できる環境が整う。
ソフトウェア開発企業は、NPUの仕様差を意識せずにAIアプリケーションを開発できるため、より幅広いデバイスでの展開が可能になる。特定のハードウェアに依存しない、汎用性の高いAI機能開発への移行を検討すべきだ。
製造業では、CSSプラットフォーム活用により開発期間短縮とコスト削減を実現できる一方で、差別化が困難になる可能性もある。付加価値創出の重点を、ハードウェア仕様からソフトウェア体験やサービス統合に移す戦略転換が求められる。
参考記事リンク
- Arm Unveils Lumex: AI on Smartphones Without the Internet? – Convergence Now
- Smarter, Faster, More Personal AI Delivered on Consumer Devices with Arm’s New Lumex CSS Platform, Driving Double-Digit Performance Gains
- Arm launches new generation of mobile chip designs geared for AI – The Economic Times
- ARM introduces Lumex: a customizable chipset design for 3nm …
- Arm bets on CPU-based AI with Lumex chips for smartphones – The Register